逆転の後編、虎を納得させられるか
「Mリーグに続く“三人麻雀のプロリーグ”を確立したい」という高田将広の挑戦は、前編で志願者の熱意と構想が披露されるも、虎たちからは実現可能性や収益性への厳しい指摘が相次いだ。
後編では、その指摘にどう向き合い、どのような反論・提案で虎たちの懸念を払拭するのかに焦点が移る。志願者・高田の言葉には、これまでの経験と信念が込められており、決して情熱だけの夢物語ではないことを証明しようとしていた。
そして、事業計画の深掘りが進む中、虎たちの評価にも少しずつ変化が現れ始める。
高田の描く「三人麻雀リーグ」の運営モデルとは
後編で最初に取り上げられたのは、リーグの収益モデルと運営の実務に関する説明である。
高田は、「プロリーグは放映権、スポンサー料、ファン課金の3本柱で収益化する」と説明。具体的には、YouTubeやTwitchなどの配信プラットフォームを活用した広告収入と、リーグスポンサーからの協賛金を柱に据える。
また、Mリーグでも導入されているファンコミュニティ(サブスクリプション型)モデルを模倣し、選手を「推す」文化を活用したマネタイズ戦略を掲げた。リーグ独自のグッズ販売やイベント開催も計画しており、「麻雀ファンの“推し活”を収益に変える仕組みは構築できる」と高田は強調する。
加えて、動画配信による「リーグの見せ方」にも意識を向け、派手な演出や実況解説の導入、視聴者参加型コンテンツなど、エンタメとしての側面を前面に押し出す方向性を提示。
これにより、従来の麻雀ファンのみならず、若年層やライトユーザーの取り込みも視野に入れている。
虎たちからの鋭い追及と、その応答
後編の中心となったのは、虎たちの厳しい質問に対して高田がどのように応じるかだった。特に槍玉にあがったのは「サンマの競技性」に関する懐疑と、「リーグ参加選手の質をどう担保するか」である。
岩井は、「三人麻雀は運の要素が強すぎて、競技としてのバランスに欠けるのでは?」と疑問を投げかけた。それに対し高田は、「確かに一局単位での波は大きいが、リーグ戦という形にすることで技術の蓄積と総合力が求められる競技になる」と応戦。
また、参加選手については、既に一部のプロ団体と非公式に接触しており、賛同を得られる見通しであることを説明。さらに、アマチュアからも登用するオープンリーグ形式を想定し、夢のあるステージとしての側面もアピールした。
虎のひとりは「これだけ準備していて、なぜ既にスタートしていないのか?」と直球の質問を投げたが、高田は「最低限の資金と協力体制がなければ失敗のリスクが高く、今がそのための最終調整段階」と冷静に語った。
情熱とビジネスのバランスはとれるのか
虎たちが最も評価を迷ったのは、「この挑戦が夢想ではなく、現実のビジネスになるかどうか」という一点に尽きる。
高田はこれに対し、麻雀人口のデータ、配信業界のトレンド、類似eスポーツリーグの収支モデルなどを挙げて、「確かに簡単ではないが、先行事例を応用すれば黒字化は不可能ではない」と説明。
さらに、「もしリーグ単体での収益が難しくても、選手育成スクールやスポンサーとのタイアップコンテンツなど、周辺ビジネスを活かせる構造を作る」と補足。事業の持続可能性を念頭に置いた発言が増え、虎たちの表情にも変化が現れる。
特にhamuは「最初は荒唐無稽かと思ったが、話を聞くうちに現実味が出てきた」と評価を改め、高田の姿勢を一定評価した。
とはいえ、虎たち全員の判断が一致するわけではなく、「ニッチ市場で勝ち切る覚悟が見えるが、果たしてそれがビジネススケールに値するか?」と最後まで懐疑的な声も残った。
麻雀界の“異端児”が仕掛ける挑戦の行方は?
後編で浮き彫りになったのは、志願者・高田将広の“情熱の強さ”と“構想の深さ”である。
三人麻雀というマイナージャンルに光を当て、プロリーグとしての地位を築くという挑戦は、現時点ではまだ多くの不確定要素を含む。だが、そこには単なる夢想ではない、明確なビジョンと実務的な準備が確かに存在していた。
令和の虎たちもまた、単なる理想論を語るだけの志願者ではないと認め、その真剣さに対して議論のトーンを変え始めた。虎たちが求めたのは「ビジネスとしての成立性」。高田はそれに対し、情熱だけでなく、仕組みや数字、競技の未来をもって応えた。
この挑戦が実現すれば、麻雀界において“第二の革命”となることは間違いない。
虎たちの最終的なジャッジは、果たしてこの挑戦に賭けるのか、それとも見送るのか。
高田将広の未来は、まさにその決断にかかっている。
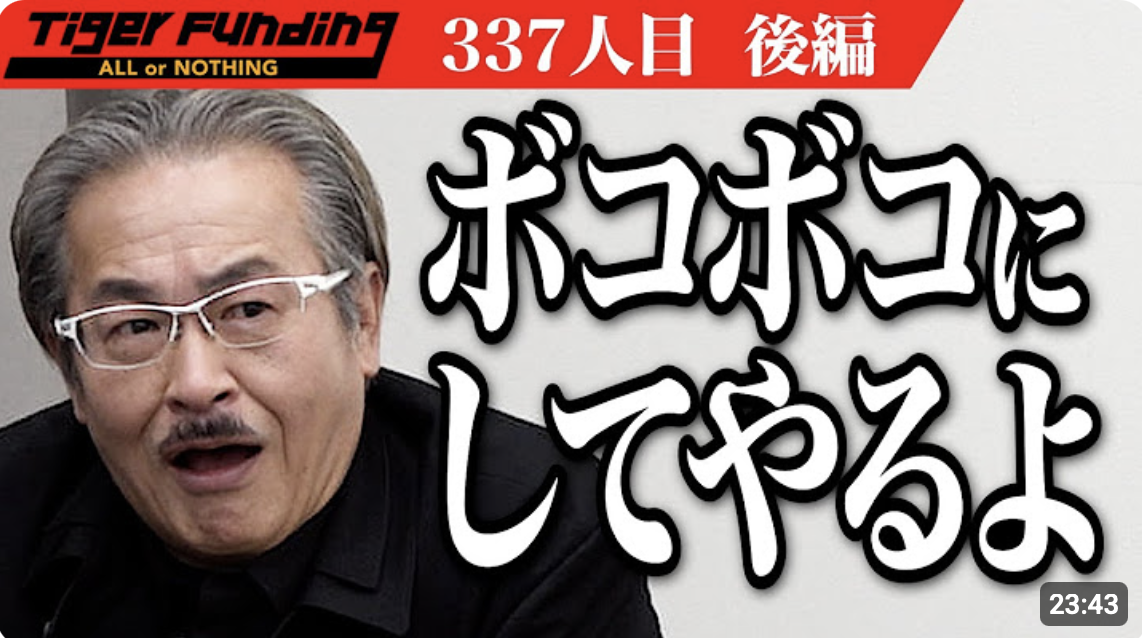
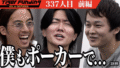
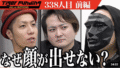
コメント